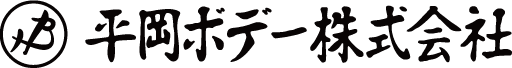フォト・ヒストリー

写真で振り返る
平岡ボデー ものづくりの源流
ここで紹介するのは、当社社員の目にもあまり触れてこなかった、貴重な創業当時の写真である。
昭和30年代、まだ自社工場を持つことができず、完成車メーカーの工場を間借りして操業していた頃から、悲願の自社工場に移転し、現在の平岡ボデーの姿と重なる企業に成長していく途上の、昭和40年代までが描かれている。
写真からも一目瞭然だが、創業当時の平岡ボデーは、現在の平岡ボデーと事業内容が大きく異なっている。
しかし同時にこれらの写真は、平岡ボデーの誇るものづくりの技術、すなわち「大物から小物までの対応力」「外装部品の仕上げ」「信頼性の高い溶接技術」といった得意分野のルーツを、創業当時までさかのぼることができることも示している。
約半世紀の時を超えて、平岡ボデーのものづくりの源流に迫ってみよう。
昭和30年代、まだ自社工場を持つことができず、完成車メーカーの工場を間借りして操業していた頃から、悲願の自社工場に移転し、現在の平岡ボデーの姿と重なる企業に成長していく途上の、昭和40年代までが描かれている。
写真からも一目瞭然だが、創業当時の平岡ボデーは、現在の平岡ボデーと事業内容が大きく異なっている。
しかし同時にこれらの写真は、平岡ボデーの誇るものづくりの技術、すなわち「大物から小物までの対応力」「外装部品の仕上げ」「信頼性の高い溶接技術」といった得意分野のルーツを、創業当時までさかのぼることができることも示している。
約半世紀の時を超えて、平岡ボデーのものづくりの源流に迫ってみよう。
「マイカー時代」の実現を支えた創業期

創業初期はボディー組立
創業当時の平岡ボデー。当時は車体の組立が中心で、供給されたプレス部品を溶接組付けして車体を組み立て、内装を取り付け、塗装まで行っていた。ほぼ完全なハンドワークで、日産30〜40台ほどだったという。
ラインは手押しで
当時の「組立ライン」は、車体を乗せた台車がなぞる“溝”を意味していた。車体の左下に見える溝をガイドにして、台車を手押ししていたのだ。この現場は、鈴木自動車工業(現スズキ)の一角にあった。
起業の想い
初代社長、平岡卯之助氏。ビジネス手腕と粋な人柄で知られ、社内外で人望を集めた。「どんなことでもいいから自動車に関わる仕事がしたい」という一念が、平岡ボデーの創業に至ったという。
初めての自社工場
昭和38年、現在の浜松市東若林に平岡ボデーとして初めての工場が建設された。本社も同時に移転し、初の「本社工場」として稼働を開始する。
人力スポット溶接
スポット溶接自体が先進技術だった当時は、重いスポット溶接機を天井から吊り、人力で動かしてパネルを溶接していた。今ではこれらの作業は全てロボットが行っているが、そのプログラムの根底にはこの時代にルーツを持つ技術ノウハウが込められているのだ。
社内もだんだん花ざかり
正確な記録は残っていないが、社内クラブも自発的に充実していったようだ。写真は華道クラブと思われるスナップ。創業から10年ほどたつと、現場にも女性社員の姿が見られるようになり、社内は賑やかだったという。
マイカーブームの到来
当時の『ディーラー』の1社。昭和39年の東京オリンピックのために高速道路が整備され、本格的なマイカーブームが始まった。それまではオートバイにキャビンをつけたような車だった軽自動車は、一気に乗用車に近づき、自動車の普及を加速していった。
「大型部品組立」へのシフトチェンジ
昭和40年代に入ると、車体丸ごとではなく、こうした大物部品の一部を組み立てて、メーカーの完成車組立ラインに納入する仕事が主流になっていった。『大物部品や外観部品に強いヒラオカ』という評価は、この時代までさかのぼることができる。
商売繁盛
平岡ボデーの虎の子だったトラックの荷台に、軽トラックの荷台アッセンブリーを4段積みしている。現代ではとても許されない大胆さだが、国内自動車登録台数がうなぎ登りだった、当時の勢いを物語っているようだ。
全員が“匠”だった
初期の軽乗用車用リヤパネルの生産風景。クランプで固定したプレス部品を、丁寧に溶接して組み立てているのがわかる。まだ治具やテンプレートというものがない時代、「ひとりひとりの技能」が品質に直結していた。組立工場から、プレス部品製造・組立メーカーへ

そして昭和40年代後半、オイルショックにより右肩上がりだった日本経済に大きなブレーキがかかる。従来のものづくりでは通用しなくなったことを悟った平岡ボデーは、価格の落ちたプレスマシンを積極導入し、部品組立メーカーから、部品製造・組立メーカーへと大きく舵を切っていく。このときの英断が、現在の平岡ボデーにつながっているのだ。