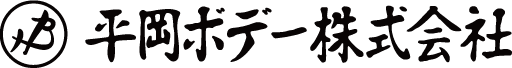若手社員緊急座談会
平岡ボデーは、次世代の
自動車業界でどう生き残る!?
2050年までにカーボンフリーな社会を実現するために、純ガソリン車の新車販売を禁止するという政府目標は、我が国の産業構造を大きく塗り替える可能性がある。
業界の再編が必至と見られる中、未来の自動車に平岡ボデーはどう関わっていくのだろうか。
当社の未来を担う若手社員がざっくばらんに語る、平岡ボデーの近未来。

2020年入社 | 技術1グループ
ジュビロ磐田ファンの最若手。工程設計や金型の立ち上げ、製品の形状検討などを担当。最近はCADを使った解析にも挑戦している。
2019年入社 | 資材グループ
プレス製品の加工ラインで生産管理を担う。プレス機によって管理方法が異なるため、担当できるラインを増やしていくことが目下の目標。
2018年入社 | 製造3グループ
アクスル製造ライン全般を担当。入社早々にある人気車の新型が発売されて修羅場を味わったが、その経験が大きな自信につながったと語る。次世代を担う若手3人が、それぞれの立場で未来を語る
司会:現在のガソリン車に比べて、部品点数が半分以下になるとも言われている電気自動車(EV)。将来、政府目標が達成されてEVが主流になったら、自動車業界は大規模な再編が進むと考えられています。平岡ボデーの得意分野である車体部品や足回り部品はEVにも欠かせない部品であるとはいえ、その影響は免れないかもしれません。そこで、本日はこれからの平岡ボデーを担っていく若手社員の皆さんにお集まりいただき、平岡ボデーの未来像を考えてみたいと思います。
それでは本題に入る前に、皆さんがどんなお仕事をされているか教えてください。
松下:技術第1グループで、工程設計を担当しています。プレス製品は金型を使って板状の素材から立体的な形状を作り出すのですが、一度のプレスで大きな力をかけてしまうと製品に無理な力が生じて割れやキズが生じてしまいます。そこで、いくつか金型を作って徐々に力を加えることで、狙った形状を実現できるようにします。それが工程設計です。

平野:今、松下君が話していたプレス製品の素材となる「鋼板」を調達するのが、僕の所属する資材グループの役割です。資材グループで生産管理を担当しています。資材なのに生産管理?と思われるかもしれませんが、何を作るにしても資材がなければ始まりませんので、お客様からの注文に合わせて生産計画を立て、それに沿って必要な資材を発注するという流れで業務を行っています。資材の調達だけでなく、加工した製品を次工程を担うグループに渡したり、鋼材のムダが生じないように製品の加工順序を決めたりと、工場全体を俯瞰して効率的なものづくりができるよう、日々工夫しています。

古橋:僕はアクスルと呼ばれる足回り部品の製造ラインを担当しています。組立に使う治具の取り替えや消耗品の補充など、ラインの管理が主な役割です。アクスルは自動車の走りと安全を支える重要部品なので、不良品を出さないこと、次工程に流さないことが絶対の使命です。ライン全体の面倒を見る仕事なのでやることはたくさんありますが、ものづくりの最前線にいるという醍醐味を感じられる仕事だと思っています。
EV時代のキーワードは、“省電費”に直結する軽量化

司会:先ほど述べたように、自動車業界は、今大きな変革期を迎えていると言われます。皆さんも普段のお仕事を通じて、それを感じることはありますか?
松下:学生時代は自動車の進化とか未来について考えたことはありませんでしたが、平岡ボデーに入社してからは、自分のいる業界のことでもありますし、上司やお客様から軽量化や電動化といったキーワードを聞くことが多いので、自動車の将来について真剣に考えるようになりました。
平野:自動車は今、すごい勢いでガソリン車からハイブリッドに置き換わっていますよね。僕たちが作っているのは自動車のフレームになる部品なので、そういう意味ではこれからもそう簡単になくなる部品じゃないとは思っているけれど……。
松下:ガソリンエンジン単体で燃費性能を上げるのは、もう限界値に近いという話を聞いたことがあります。
古橋:平岡ボデーの仕事としては、そうですよね。僕の所では自動車用のボディ部品や足回り部品を作っているけれど、これもEVの時代になってもそんなに大きく変わるものじゃないし。
平野:ただ、車がEVに変わっていくと、もっと軽量化技術が注目されるのは間違いないですよね。自動車用の部品はたぶん、もっとシンプルでコンクパクトなものが求められるようになっていくと思いますので、当社の製品であるボディ部品や足回りの作り方にも、今以上に影響は出てくるのだろうと感じています。
松下:以前から省燃費のための軽量化ニーズは高くて、カーボンファイバーや樹脂素材への転換もたびたび話題になってきました。ただ、金属──それも鉄という素材の利点は、そう揺らがないと思うんですよ。ボディは単に軽ければいいというものじゃなくて、乗員を守る強さが何よりも優先されます。鉄と同じような強度、加工性、そしてコストを実現できる新素材が出てくるのは、もう少し先なのかなと思っています。

平岡ボデーが挑むのは、“省コスト”と“鉄の可能性”
司会:それでは、平岡ボデーはこれからも安泰ですね。
平野:いやいや、安泰ということはないです!(笑)。僕は、平岡ボデーが果たさなければならない役割は2つあると思っています。1つはより低コストで同品質の製品を作ること、もう1つは“鉄”という素材の可能性をさらに追求することです。
古橋:鉄の可能性を追求する、という部分は技術の方が中心になる要素だと思いますが、コストに関しては全部門の共通目標と言えるのではないでしょうか。僕たちの世代が自動車の価格を意識したのは、当然ながら自分たちが免許を取ったここ数年のことになるわけですが、もっと上の先輩たちが社会人になりたての頃に乗っていたという車の話を聞くと、自動車の価格は全体的に高くなったんだなあと実感しますよね。
平野:もちろん、当時とは基本的な性能、特に安全性能と燃費性能は比べものにならないので直接比較は難しいでしょうが、どんなに性能が高まっても、一般の方に手の届かない存在になってしまったら意味がない。それは、これから生まれてくるであろう、より環境性能の高い車に関してもそうですよね。「いい車をより安く」は、自動車がこれからも庶民の乗り物として存在していくための、業界全体の課題だと思います。

司会:コストの話になると、皆さん熱がこもりますね。皆さんの職場では、コストを下げるためにどんな取り組みをされているのですか?
平野:資材では、いかにムダを出さないかを常に考えていますね。鋼材って同じように思えて実はけっこう水モノなんです。必要なサイズや品質の鋼材がいつでも手に入るかというとそうではなく、その時その時で最適な仕入れをしなければならない。当社で一番使うのはプレス用の鋼板で、これは鉄板をロール状に巻いた形で届きます。鉄鋼所では、それこそ日本中の工場で使われる大量の鋼板を製造していますが、注文したものが即時に生産されるというよりは、製造されて保管されている製品の中から、希望の製品を探して仕入れるというイメージです。なので、先の需要を見越して発注するのですが、鋼板は保管が難しいので、何でも買っておけばいいというわけでもないのです。
松下:材料の保管って難しそうですもんね。鉄だから錆びやすいし、大きいし。
平野:営業やお客様からなるべく多くの情報を仕入れて業務の効率を上げ、保管の手間や無駄を省くことができれば、結果として、お客様に安く車を届けられることになりますからね。

松下:技術では、工程や形状を考える中で、CADを使った解析が進んでいます。試作する前に机上で問題を潰すことができるので、生産リードタイムを短縮することができます。自動車用部品の要求精度は年々高まっているのですが、最近は形状の精度も厳しく求められるようになりました。車は部品点数が数万とありますが、それぞれの公差がわずかでも、組み合せるとズレは大きくなる。ズレは強度や性能に影響してくるので、トータルで公差を小さくするためには一つ一つの部品の精度を高めるしかない。以前のやり方では試作と再調整でかなりの時間を必要としていたので、スピードやコストはかなり改善されていると思います。
古橋:製造の使命は、生産性を上げることと不良を出さないこと、この2つに尽きますので、これまでと取り組み自体は変わりません。ただ、自動車業界はどこも人手不足で、さらにコロナ禍が追い討ちをかけて新車のバックオーダーがすごいことになっています。ウチだけが頑張れば済む問題でもないですが、たぶんどこの会社の製造技術も限られたリソースの中でいかに生産性を上げるか、がむしゃらに頑張っているはず。コスト改善をしつつ、サプライチェーンのブレーキにならないよう、とにかくものを作り続ける。今はそれが最優先ですね。
鉄の可能性を広げることが、自動車設計の自由度を高める
司会:もう一点の、“鉄という素材の可能性”という部分ではいかがでしょうか?
松下:平野さん、資材の目から見て、超ハイテンの仕入れが増えているとかあります?
平野:量産ベースでは増えていませんが、注目が集まっているのは感じていますね。
松下:僕は材料の知識は少ないのですが、今、業界全体が超ハイテンの利用率をどんどん上げようとしています。超ハイテンは、かつてはプレス不能とまでいわれたほど固い鉄板なのですが、当社でもCAD解析を駆使して、だんだん複雑な形状にも対応できるようになってきています。実際に超ハイテンをどう使うかはメーカーの方が決めることですが、当社のようなプレスメーカーが超ハイテンの加工技術を高めることで、自動車設計の自由度を広げることができます。そういう意味で、平岡ボデーが“鉄の可能性”を広げていくことが可能だと考えています。
古橋:製造部としては、超ハイテンを使った歩留まりや作業効率が未知数なので、まだ現実感がないというのが正直なところです。新製品の量産が近づいてきたときのために、今できることを進めるのが大切なのかなと考えています。

松下:当社は自動車メーカーの技術者とも比較的近いポジションにいて、お互いに相談しながらよりいい製品を作っていこうという協力関係にあります。自分の働きが、わずかでも自動車の進化を支えられたらうれしいですよね。

チームワークで挑み続ける会社、それが平岡ボデー
司会:平岡ボデーが、これからの自動車業界の中でも、確固たる存在感を持って活躍していけることがわかりました。最後に、皆さんが思う「平岡ボデーのいいところ」について教えてください。
古橋:職場の風通しが良くて、何でも言い合えること、かな。
平野:基本的に、助け合いの精神がありますよね。日々の業務も、新しいことを始めるのも、それが原動力なんじゃないでしょうか。
古橋:「TEAM HIRAOKA」ですね。
松下:加えて、僕は挑戦をいとわないマインドも挙げておきたいです。困難なことも多いですが、そうした新しいことに挑戦するための困難なら、かえって楽しんでしまえという気概もありますよね。みんなで挑戦する会社、平岡ボデーがそういう集団である限り、新しい時代にも十分に対応していけると信じています。